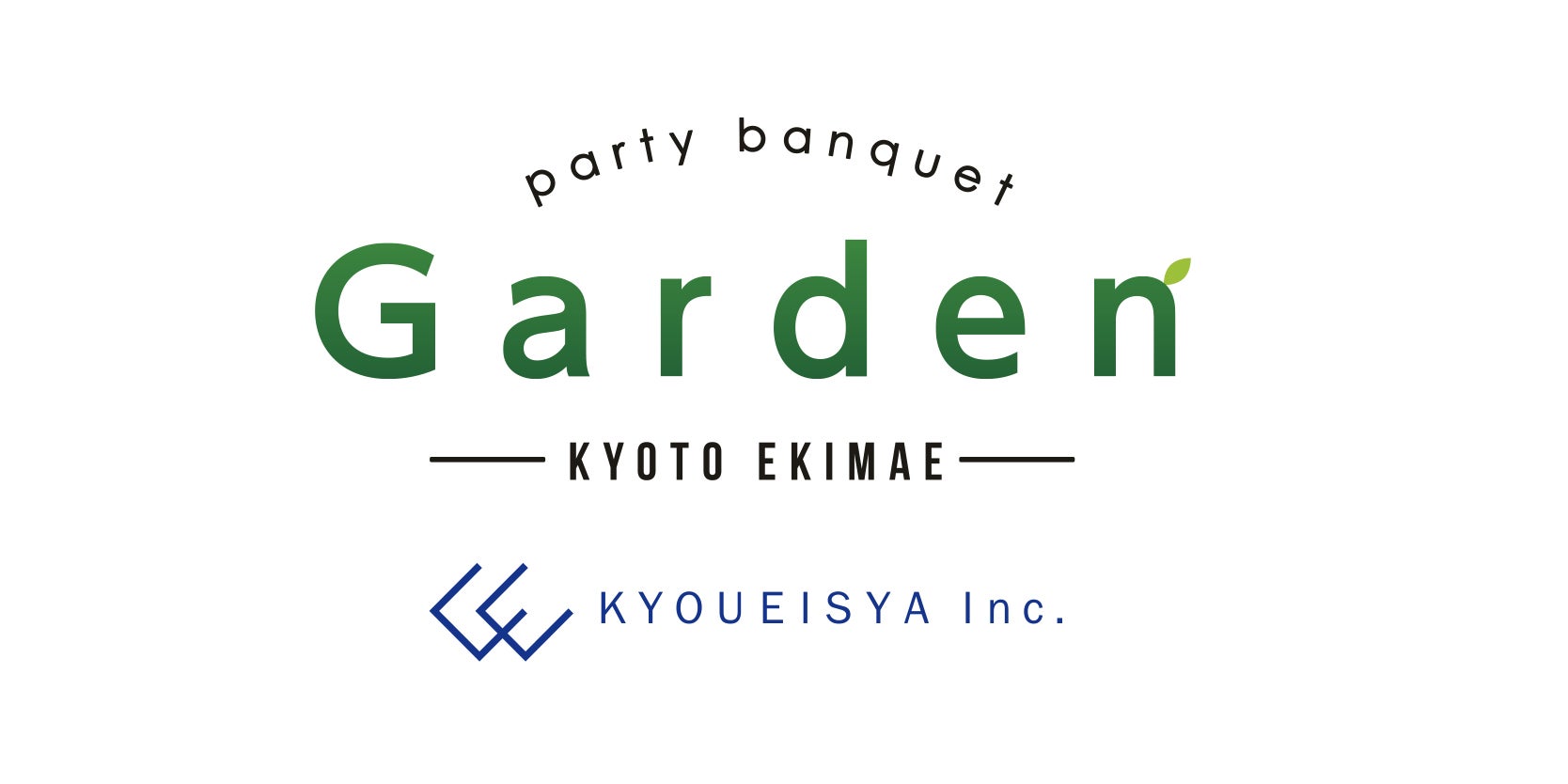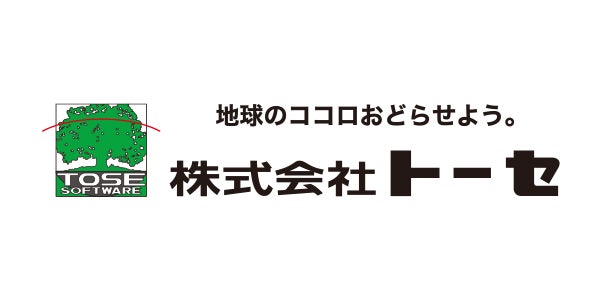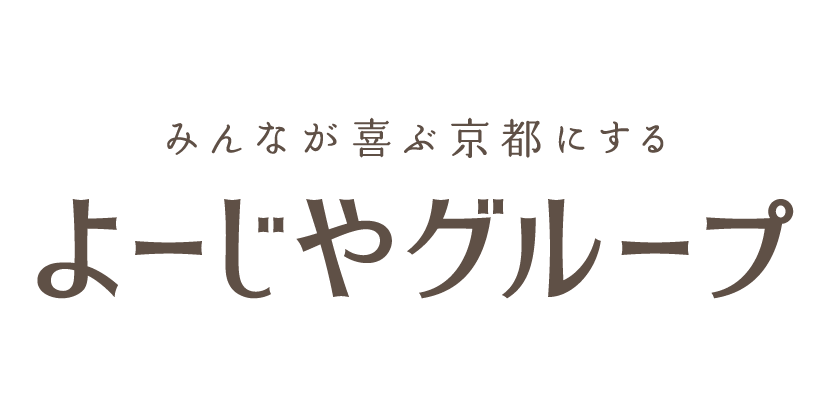ユース特別企画「綿貫瞬U18AC 育成への決意」
2024年8月から、京都ハンナリーズU18に、通算5シーズンにわたって京都ハンナリーズでプレーした綿貫瞬アシスタントコーチが就任しました。
現役時代のポジションはポイントガードで、冷静にゲームを組み立てるタイプの司令塔でありながら、信条としたのは泥臭いプレー。ルーズボールに身体を投げ出したり、外国籍選手が居並ぶリバウンド争いに果敢に飛び込んでいくなど、熱意を感じさせるプレーでブースターを湧かせました。
プレーヤーとしては2023−24シーズン限りで引退しましたが、現役晩年からアンダー世代を指導することに関心を抱き始めます。
綿貫U18ACは、学生時代からエリート選手ではありませんでした。そこから這い上がり、プロとして10年以上プレー。自らの経験を若い世代に伝え、多くの良い選手を育てていく決意をストーリーにしました。
内海慎吾ユース統括ディレクターから突然の電話、それがきっかけだった
Bリーグの2023-24シーズンが終わって、少しの時間が経ったころ。綿貫瞬の携帯電話が、不意に鳴った。発信者名に目をやると「内海慎吾」とある。京都ハンナリーズ時代の、チームメイトだ。ハンナリーズ在籍時は内海との関係は良好だったが、頻繁に食事に出掛けるような間柄ではなかった。だから「なんだろう」という思いを持ちながら、通話のボタンを押した。
そのころは最後にプレーしたレバンガ北海道を最後に、現役を引退することで気持ちは固まっていた。引退後はバスケットボールで伸び悩んでいるアンダー世代のために何かできないかと模索していた。内海からの電話は、そんな時期にかかってきた。
久しぶりの挨拶もそこそこに、内海は本題を切り出す。「ユースのコーチが辞めることになって、後任を探している。引退して、こっちに来る気はないか」。内海が2020-21シーズン限りで現役を引退し、ハンナリーズのユースチームのコーチングスタッフになっていたことは、もちろん知っていた。その内海からの誘いに、綿貫は即答した。「行きます」と──。
「ウインターカップや全国大会に出たりするような、上手いコたちはいいんですよ。でもほかに、くすぶっているようなコたちもいると思うんです。そういうコたちにしっかりとしたバスケットを教えて、上のレベルに上げてやりたい。それをしたいと、以前から思っていました」
指導者を志した根底には、自身が歩んできたバスケ人生が大きく関わっている。
「僕が通った高校は、近隣の中学校から生徒が集まるような普通の高校だったんです。バスケ部もいわゆる部活で、大会ではだいたい1回戦負けするようなレベルでした。だけど僕が3年生のときに、すごい能力がある選手がいたわけでも、特別に上手い選手が入ってきたわけでもないのに、神奈川県で優勝して初めてウインターカップに出たんです」
そうなったのには高校の指導者の存在が果たした役割が大きいのだが、詳細は後述する。綿貫自身は進学時に推薦で神奈川大に進んだが、当初は実力を過小評価されていた。
「同い年の推薦で入ったコたちはほぼAチームでやっていたのに、僕は最初はずっとBチームだったんですよ。でもそこで腐らずに自分のプレーをやっていたらすぐAチームに上がって、1年生だけどスターティングメンバーで試合に出るようになりました。僕はエリートだったわけではありません。自分で這い上がってきた経験から、今は上手くできていないコたちを僕の手で上にあげていきたい。いつからか、そういう気持ちが芽生えてきたんです」
自分に寄り添い、自信を与えてくれた 高校時代の恩師の指導が自身の礎
現役時代はさほど、アンダー世代の選手と関わることはなかった。それでも数少ない接点で、気付いたことがある。その際の目線は、指導者のそれだった。
「オフシーズンに地元の神奈川に帰って母校や知り合いの高校や、恩師である先生の高校に行くことはありましたが、それほどたくさんは関わっていません。でも行く機会があれば、選手たちを『もっと、こうしてあげたらいいのに』みたいな目では見ていましたね。言い方は悪いですが『こういう教え方しかできないのか』とか『こうすれば、もっと上手になるのにな』と思っていました」
いつのころからか現役でプレーしながら、アンダー世代を指導することが頭のなかに浮かび始めた。現役で得た経験が、活かせるのではないかと。
「現役を長くやらせてもらいましたが、トップチームは1年ごとにメンバーが替わるんです。そのたびに僕は、チームメイトの分析をしました。この選手はこういうタイプ、この選手はこうと。その経験から、いろんな人の感覚がわかるようになってきたんです。だからアンダー世代の選手でも、間違ったプレーや身体の使い方をしていたら気付ける。それぞれのコに合った指導を、やっていきたいなと思ったんです」
トップチームのコーチになることには、さほど関心はない。アンダー世代でも小学生以下ではなく、中高生年代は自分にもっとも適していると感じている。
「まずはバスケットをもっと好きにさせるのを大前提に、上手くプレーするための技術や体の使い方なんかを教えてあげる。このふたつをしっかりとやって、バスケットを上手にさせる。僕の考え方の根本にあるのは、それなんです。とくに中学生、高校生の年代はそれが、いちばん大事だと思うんですよ。アンダー世代を教えることは僕がやりたかったことですし、自分に適していると思います」
これまで現役選手としてプレーしてきて、多くの指導者と出会ってきた。なかでももっとも影響を受けたのは、高校時代の監督だったという。
「影響を受けた指導者の方は、たくさんいます。いちばんは、高校時代の深田先生ですね。深田先生は僕のことを、ずっと信用してくれていたんです。僕はキャプテンだったのですが、なにをやろうとも信用してくれて、否定をしなかった。小学生、中学生のころは自分が厳しい指導を理解できずに、自信を持てないでいたんです。だけど深田先生はずっと寄り添ってくれて、自信をくれて、否定しないでやらせてくれた。それが僕には、すごく大きかったですね」

選手ひとりひとりに寄り添い、プロで経験したことを伝えていく
プロとして10シーズン以上のキャリアを重ねてきたが、指導者としては1年生。自らもコーチとして成長しなければいけないことは、充分に自覚している。
「アシスタントコーチの立場なので、ヘッドコーチをサポートする役割がメイン。それをわきまえたうえで、とにかく熱くやろうと思ってます。指導者に転身したばかりですし、今は自分もコーチの勉強をする期間。練習時間が限られているのでタイムマネージメントをしながら、そのなかでどうやって大切なことを教えるのかなど、いろんなことを学んでいる最中です」
さらに、決意を込めた言葉を紡ぐ。
「ユースチームはアンダー世代といえど、勝負がかかっています。でもここで終わりではなく、彼らには先に続く未来がある。それを見据えたうえで適切なコーチングができるように、僕自身も成長していかないといけない」
ひと昔、ふた昔前は選手を怒鳴って、自分のやり方を押し付けてという指導者がいたことは事実。さすがに今の時代は、そんな指導法は通用しない。そんな現代だからこそ、彼が高校時代に大きな影響を受けた恩師の指導法は、大いに参考になるのではないだろうか。
「深田先生はあらかじめ選択肢をたくさん用意して、その場で考えなさいという教えだったんですよ。ひとつだけではダメ。ふたつ、3つと選択肢を持って、プレーしなさいと。自分たちで考えながらプレーしないといけないので、すごくためになりました。それがあるから今も、選手たちにはピックアンドロールにしても、プレーするときは必ず選択肢を作りなさい。そうするとターンオーバーも減るし、プレーの質も上がってくると伝えてます」
ユースチームに集まる選手たちの意識はそれぞれで、個々の向上心に差違もある。心身ともに成長過程であるがゆえ、道に迷うこともある。そんな彼らに綿貫は、高校時代の恩師が自分にそうしてくれたように、選手ひとりひとりに寄り添っていく。
「U18のアシスタントコーチを務めるようになって、1ヶ月くらい経ったころからですかね。僕のところに『どうしたらいいですか』とか、『やり方がわからないです』などと訊いてくるコが増えてきたんですよ。選手から訊きに来てくれて、彼らは僕が教えたことをやろうとしている。僕のコーチとしての一歩が始まったと感じて、すごくうれしく思いました。コーチとしてはまだ未熟ですが選手ひとりひとりに寄り添い、僕がプロの現場で経験したことを伝えて、彼らが成長する力になっていきます」
- 文・カワサキマサシ -